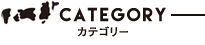獣医師の山本です。
6月16日から20日の5日間、大学の学生臨床実習の一環で学外で実践的な実習を行う「参加型臨床実習」を昨年に続いて1名受け入れました。
受け入れた学生さんは大学院進学希望でしたが臨床が好きで、学内の実習ではなく実際の現場を学びたいということで当院を希望してきました。
普段受け入れている学生実習は、現場を体験し、知多大動物病院を体感してもらうために、毎日同行する獣医師が変わりますが、参加型臨床実習はメインの指導獣医師を決めて基本的には1人の獣医師が指導する形式になり、事前に指定された実習項目一覧表があって現場で診療しながらそれをこなしていきます。今回も過去2回と同様、私が担当しました。
必修項目として21項目、例えば保定、TPR、各部位の聴診、触診などといった基本的なこと、アドバンスとして32項目、例えば採血、注射、留置針、手術の皮膚切開、皮膚縫合、心エコー、繁殖エコー、採卵、分娩介助など多岐にわたる臨床技術があります。
必修項目は1日で大半終わらせて、アドバンスはその学生がどれだけ引きが強いかにかかってきますが、今回の学生さんは強力だったのでアドバンスを26項目クリアしていきました。
ちょうど暑さが増したころだったので毎日たくさん汗をかいて頭と体をフル回転し、夜には1年目の獣医師も一緒に食事に行ってお腹いっぱい食べていろいろお話もして、しっかり休んで、また昼間はしっかり頭と手を動かす実習する充実した5日間だったと思います。
実習期間中に私が実施した新人獣医師用ケトーシス院内勉強会を1年目の獣医師と一緒に受けてもらました。
実習から帰ったら症例発表会があるとのことで、現場的でやや複雑な症例を毎日診ていたのでその症例にしました。乳房炎とケトーシスと創傷性第二胃腹膜炎を併発している牛でした。
5月から稼働した搾乳ロボット牛舎での症例だったのでロボットから様々な情報を取れたことに加え、血液検査、乳汁細菌検査、腹部超音波検査も実施して情報量が多い分、発表としてまとめるのが大変だろうと思いましたが、一緒にその牛を診ていた1年目獣医師と私と3人で事前にディスカッションもできたし、帰ってからもいくつか質問をやり取りしつつその後の経過も伝えたので、かなり充実した発表になったようです。
発表会では大学の先生方も一緒に症例検討するような場となったそうで、現場的ないい症例だったという言葉をいただけたとの報告をくれました。
ここまで充実した実習をやる学生は少数派だとは思いますが、どうせ単位取得のために臨床実習を履修するなら、学外に出て現場の臨床獣医師の指導のもとで実際に頭と体を動かして実習した方が実習としての価値が何倍も高いと思います。学内と学外を選択できるなら学外をお勧めします。
大動物臨床を知らないという学生さんも、実際の現場を知らないまま卒業するのはもったいないので、大学の近くでも実家の近くでもネット検索でも大学の先生や先輩の紹介でも何でもいいので、一度体験してみるといいです。
私の身近な人や友人や知人の中にも、とりあえず行ってみたら「これだ!」と感じてしまってその道に進んだ人もいます。そうでない人でも思い出話くらいにはなります。
入学当初に決めていた進路一本にこだわらずに学生のときにいろんな道をのぞいてみた方がいいと思います。
まだ知らないおもしろい世界があるかもしれませんよ。
 肥育牛角神経ブロック:鎮静、鎮痛や局所麻酔は牛と人のお互いの安全のためでもある
肥育牛角神経ブロック:鎮静、鎮痛や局所麻酔は牛と人のお互いの安全のためでもある
肥育牛除角:鎮静と角神経ブロックのおかげで切っても焼いても痛くない